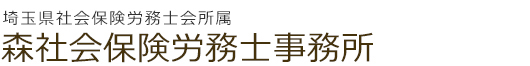労働基準法
労働基準法は労働条件の最低基準を定めた法律です。労働契約、労働時間、賃金、休憩、休日、災害補償、就業規則等について定められています。
労働基準法上の「労働者」とは
職種を問わず、事業又は事業所に使用される者で、賃金を支払われる者。
使用者の指揮命令を受けて働き、賃金を支払われる者は、正社員・パート・アルバイト・有期雇用などの雇用形態や職種を問わず全員が労働基準法が適用される「労働者」です。
労働契約を結ぶときの労働条件の明示事項について
労働基準法では「使用者は、労働契約の締結に際し、労働者に対して賃金、労働時間その他の労働条件を明示しなければならない。」と定められています。
明示すべき事項は以下の通りです。赤字で記載している事項は書面を交付して明示しなければいけません。
- 労働契約の期間に関する事項
- 就業の場所及び従業すべき業務に関する事項
- 始業・就業の時刻、所定労働時間を超える労働の有無、休憩時間、休日、休暇、労働者を2組以上に分けて就業させる場合には就業時転換に関する事項
- 賃金(退職手当と臨時に支払われる賃金等を除く)の決定、計算、支払いの方法、締切日、支払日、昇給に関する事項
- 退職に関する事項(解雇事由を含む)
- 退職手当の適用される労働者の範囲、退職手当の決定、計算、支払いの方法、支払いの時期に関する事項
- 臨時に支払われる賃金(退職手当を除く)、賞与及びこれらに準ずる賃金、最低賃金額に関する事項
- 労働者に負担させる食費、作業用品その他に関する事項
- 安全及び衛生に関する事項
- 職業訓練に関する事項
- 災害補償及び業務外の傷病扶助に関する事項
- 表彰及び制裁に関する事項
- 休職に関する事項
パートタイム労働者を雇い入れたときは、上記に加えて次の3点を文書の交付等で明示することが義務付けられています。
・昇給の有無
・退職手当の有無
・賞与の有無
就業規則について
賃金や労働時間、人事、服務規律など、労働者の労働条件や待遇の基準を定めたものが就業規則です。あらかじめ基準を定めておくことで、労使間の無用なトラブルを防ぐことに繋がります。
常時10人以上の労働者を雇用している使用者は、就業規則を作成し、労働基準監督署に届け出なければなりません。
※ 労働者が10人以上いるかどうかは法人単位ではなく、事業場単位で判断します。例えば2つの工場を有している法人が両工場とも10人未満である場合には、法人単位でみた場合は10人以上であったとしても就業規則の作成義務は生じません。
【絶対的必要記載事項と相対的必要記載事項】
就業規則に記載する事項には、絶対的必要記載事項と相対的必要記載事項とがあります。この他に、使用者が任意に記載し得る事項もあります。
①絶対的必要記載事項・・・就業規則に必ず記載しなければならない事項
・始業および終業の時刻、休憩時間、休日、休暇、交替制勤務の場合の就業時転換に関する事項
・賃金の決定、計算及び支払いの方法、締切日、支払日、昇給に関する事項
・退職に関する事項(解雇の事由を含む)
②相対的必要記載事項・・・ルールを定める場合には記載しなければならない事項
・退職手当が適用される労働者の範囲、決定、計算、支払いの方法及び支払いの時期に関する事項
・臨時の賃金、最低賃金額に関する事項
・労働者に負担させる食費、作業用品、その他の負担をさせることに関する事項
・安全及び衛生に関する事項
・職業訓練に関する事項
・災害補償及び業務外の傷病扶助に関する事項
・表彰及び制裁の種類、程度に関する事項
・事業場の労働者すべてに適用されるルールに関する事項
【就業規則の作成・変更手続き】
就業規則を作成したり変更する場合の届出には意見書を添付します。
意見書は、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合は労働組合、労働組合が無い場合は労働者の過半数を代表する者の意見を記入します。
【就業規則の周知】
作成した就業規則は、労働者に周知しなければなりません。
周知は、一人一人へ配布、職場の見やすい場所へ掲示する、社内イントラネット等で常時閲覧可能な状態にするなどの方法が認められています。
お問い合わせはこちら

労務管理の新着情報 更新中!
●インターネットやSNSに労働者の募集に関する情報を載せる際は注意してください(2025.1.21)
●40歳になられた方へ「介護保険制度」について(2024.12.20)
●カスタマーハラスメント対策に取り組みましょう!(2024.12.13)
●子の看護休暇等の「取得事由の拡大」について(2024.12.6)
●育児・介護休業改正ポイントのご案内(2024.12.2)
●高年齢雇用継続給付の支給率が変更されます(2024.11.21)
●育児休業給付金の支給申請手続きを行う事業主の方へ(2024.11.11)
●フリーランスの取引に関する新しい法律が11月にスタート(2024.10.28)
●「外国人雇用管理セミナー2024」のお知らせ(2024.10.24)
●令和6年10月から教育訓練給付金が拡充されます(2024.10.18)
代表者
特定社会保険労務士
森 順子