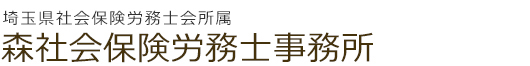社会保険・労働保険の手続代行
社会保険(健康保険・厚生年金保険)の手続き
社会保険の新規適用手続きから被保険者資格の取得・喪失手続き、傷病手当金や出産手当金の申請、定時決定、給与の変更に伴う標準報酬月額の改定手続き等の申請を代行します。
また、給与から控除する保険料の計算や、保険料率の変更、法改正など最新の情報を提供します。
★社会保険は、法人の場合は必ず加入しなければなりません。代表者1名のみの会社であっても、加入する必要があります。
★個人事業の場合は農林水産、サービス業など一部の業種を除き、従業員が常時5人以上の場合には加入する必要があります。
労働保険(雇用保険・労災保険)の手続き
労働保険は正社員、パート、アルバイトを問わず労働者を1人でも雇用している場合は、法人、個人事業主を問わず加入が義務付けられています。
保険関係成立届、適用事業所設置届等の提出手続き、労働保険料の申告及び納付に関する手続き(年度更新)、被保険者資格取得届、喪失届(離職票の発行)手続き、育児休業給付金、高年齢雇用継続給付金の手続き、労災保険の給付に関する手続き等を代行します。
このような時にはご相談下さい!
- 社会保険、労働保険に関する手続きが分からない
- 人手不足で事務処理、届出手続きを行う事が難しい
- 事業主や家族従事者が労災保険に入りたい
- 出産、育児・介護休業をする従業員がいるので、休業や給付金について知りたい
- 適用拡大について知りたい
★当事務所では手続きの代行業務をさせていただくだけではなく、貴社と従業員の方にとってより良い形になるようサポートします。
★電子申請に対応しています。ほとんどの手続きで押印不要、スピーディーな申請が可能です。
★ペーパーレスを推進している企業様、テレワークをしている企業様等、ご希望をいただいた場合は申請控え等の公文書を電子データで送信いたします。
Q&A
社会保険の適用拡大とは?
現在、従業員数501人以上の企業で働く一定の要件を満たすパート・アルバイトについて社会保険の加入が義務となっています。
令和4年10月からは従業員101人以上の企業、令和6年10月からは51人以上の企業で働くパート・アルバイトも加入が義務化されます。
加入対象となるのは以下の要件を全て満たすパート・アルバイトの方です。
・週の所定労働時間が20時間以上
・月額賃金が8.8万円以上
・2か月以上の雇用の見込みがある
・学生ではない
労災保険の特別加入とは?
労災保険には中小事業主や一人親方の特別加入制度があります。
この制度に加入すると労働者と同じ業務をしていた時の労働災害であれば、事業主でも労災保険の給付を受けられます。
加入は労働保険事務組合経由で手続きする必要があります。
特別加入を希望する中小事業主、建設業・運輸業の一人親方の皆様の手続きについて、詳細は当事務所にお問い合わせください。当事務所は労働保険事務組合(埼玉SR経営労務センター)の加入員です。
労災事故発生時に労働保険に未加入だったら?
事故にあった労働者は労災保険の給付を受けられます。事業主は遡って保険料を徴収される他、給付金額の100%又は40%が費用徴収されます。
人事労務関係の書類の保存期間について
| 項目 | 書類の名称 | 保存期間 | 起算日 |
| 人事関連 | 労働者名簿 | 3年 | 労働者の死亡,退職又は解雇の日 |
雇入れに関する書類 (労働契約書,労働条件通知書,履歴書等) | 3年 | 労働者の退職又は死亡の日 | |
退職解雇に関する書類 (退職届,解雇通知書等) | 3年 | 労働者の退職又は死亡の日 | |
| 賃金台帳 | 3年 | 完結日(賃金支払日が完結日より遅い場合は、賃金支払日) | |
| 労働時間等の記録に関する書類 (出勤簿,タイムカード,残業命令書,報告書等) | 3年 | 完結日(賃金支払日が完結日より遅い場合は、賃金支払日) | |
| 36協定の協定書等 | 3年 | 協定の有効期間満了日 | |
| 賃金その他労働関係に関する重要な書類 | 3年 | 完結日(賃金支払日が完結日より遅い場合は、賃金支払日) | |
労働保険 関連 | 災害補償に関する書類 | 3年 | 災害補償を終わった日 |
労働保険に関する書類 (徴収法等による書類を除く) | 3年 | 完結日 | |
雇用保険に関する書類 (被保険者関係の書類を除く,代理人選任届等) | 2年 | 完結日 | |
| 雇用保険の被保険者に関する書類 | 4年 | 完結日 | |
| 労働保険料の徴収・納付に関する書類 | 3年 | 完結日 | |
社会保険 関連 | 健康保険に関する書類 | 2年 | 完結日 |
| 厚生年金保険に関する書類 | 2年 | 完結日 | |
安全衛生 関連 | 一般健康診断個人票(雇入れ時健康診断、定期健康診断等) | 5年 | 作成日 |
安全委員会・衛生委員会・安全衛生委員会の議事録 | 3年 | 作成日 | |
| 救護に関する訓練の記録 | 3年 | 作成日 | |
| 特別教育の記録 | 3年 | 作成日 | |
| 機械等の定期自主検査 | 3年 | 検査実施日 | |
| 退避等の訓練の記録 | 3年 | 作成日 | |
| 騒音の測定等の記録 | 3年 | 作成日 |
※”完結日”の起算日については定めがないものもあり、それぞれの保険者判断で決められています。
※労働基準法109条の改正により「使用者は、労働者名簿、賃金台帳及び雇入れ、解雇、災害補償、賃金その他労働関係に関する重要な書類を5年間保存しなければならない。」と定められていますが、経過措置として当分の間は3年が適用されます。
お問い合わせはこちら

労務管理の新着情報 更新中!
●インターネットやSNSに労働者の募集に関する情報を載せる際は注意してください(2025.1.21)
●40歳になられた方へ「介護保険制度」について(2024.12.20)
●カスタマーハラスメント対策に取り組みましょう!(2024.12.13)
●子の看護休暇等の「取得事由の拡大」について(2024.12.6)
●育児・介護休業改正ポイントのご案内(2024.12.2)
●高年齢雇用継続給付の支給率が変更されます(2024.11.21)
●育児休業給付金の支給申請手続きを行う事業主の方へ(2024.11.11)
●フリーランスの取引に関する新しい法律が11月にスタート(2024.10.28)
●「外国人雇用管理セミナー2024」のお知らせ(2024.10.24)
●令和6年10月から教育訓練給付金が拡充されます(2024.10.18)
代表者
特定社会保険労務士
森 順子